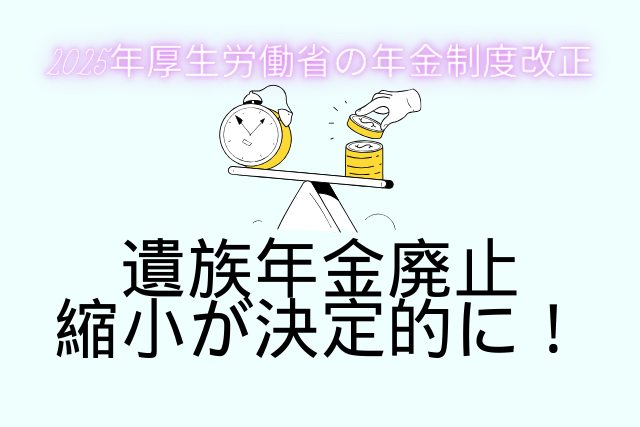2025年の年金制度改正に向けて、遺族年金廃止の方向で議論されるそうです。
少子高齢化や就労状況の変化に対応した制度改善が急務ということですので、全くありえない話ではないようです。
厚生労働省は働き方に関係なく公平な年金制度への改革を進める。2025年に迎える5年に1度の年金制度改正で、遺族年金の男女差の是正や厚生年金の短時間労働者への適用拡大などを検討する。少子高齢化や就労状況の変化に対応した制度改善が急務となっている。
女性の社会進出が広がり、会社員の夫と専業主婦の妻というモデル世帯はすでに主流ではなくなっている。いまでは夫婦世帯の3割ほどにとどまり、ピーク時から半減し…
日本経済新聞
すぐに完全廃止とはならないと思いますが、縮小の方向で動くのは間違いありません。
公認会計士山田真哉さん
公認会計士の山田真哉さんという有名な方がいらっします。
『さおだけ屋はなぜ潰れないのか?』『女子大生会計士の事件簿』など、多くのベストセラーを生み出しているので、
ご存知の方も多いと思います。
女子大生会計士の事件簿 Season2 (前編)  Audible版 – 完全版
Audible版 – 完全版
Audible版ですと、今なら無料です。
山田真哉さんのyoutube
最速】2025年年金改正直前!遺族年金、見直し廃止論議。現役世代も影響大【会社員・社会保険・基礎・厚生/生命/計算方法・受給資格/老齢・
というタイトルで、youtubeにアップされています。
2024/04/21にアップしたばかりなのに、1,297,381 回視聴 (6/11日現在)です。
関心の高さがうかがわれます。
要約 ・遺族年金は問題点や矛盾点が山積しており、今回の改正で全てが一気に変わるわけではないと思いますが、長年かけて制度変更されていくかと思われます。
・これまでの流れを考えると、すでに遺族年金をもらっている方については影響が出ないような改正になるかと思われます。
との内容です。
今もらっている人
今現在、遺族年金をもらっている人には、あまり影響がないと思われます。
しかし、本当に年金制度を破綻させないために、減額という可能性もあり得るのではないのかと思います。
近未来は廃止の方向
遺族年金は廃止、第三号被保険者廃止に向かいます。
向かっていることは、間違いないです。
【2024年金改正速報】「主婦年金廃止!年15万円の負担増」とは。年収106万円の壁 改悪いつから。
2016年からスタートした「106万円の壁」での社会保険加入条件は、「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大」と呼ばれています。
遺族年金の見直し・廃止論議→「【最速】2025年年金改正直前!遺族年金、見直し廃止論議。現役世代も影響大」https://youtu.be/GwD5Ezw63ZQ ・年金が6万円増えるという話は、年間で6万円です(そもそも、年間でもらえるお金だから『年金』) ・社会保険に加入する場合、健康保険・厚生年金はセットで加入することになります(つまり、配偶者の健康保険・厚生年金の両方の扶養から同時に外れる)。 ・社会保険加入条件における会社の従業員数は、社会保険の「被保険者数」で判断します。
↓
社保適用範囲の拡大→「【超速報】年金・保険大激変!全事業所、パート週20時間勤務で扶養除外、個人経営・フリーランスも社会保険加入へ」 https://youtu.be/7DijbgoH9OU
どんどん扶養除外になってきていますね。
年収の壁70万円
もし年収の壁が70万円になる場合
年収70万円にかかる社会保険料は約14万円(東京都在住、介護保険第2号被保険者に該当する場合)です。
年収70万円を超えるのであれば、年収84万円以上稼がなければ手取りを増やすことができません。
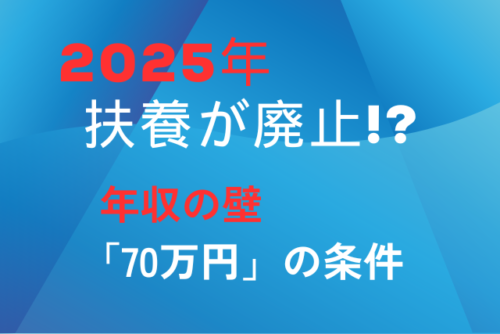
人生何があるかわからない
100年安心とは、日本の公的年金制度が100年安心ということだったらしいのです。
それが、、“公的年金だけで老後の生活は100年安心である”と思い込まされてしまったと。
公的年金制度は100年経っても破綻しないという意味の“安心”だったはずである。決して個人が「100歳まで老後の生活は安心できる」などといった説明そもそもされていないそうです。
興味深い記事です。
執筆者は ニッセイ基礎研究所金融研究部 取締役 研究理事 兼 年金総合リサーチセンター長 兼 ESG推進室長德島 勝幸さんです。
公的年金の「100年安心」は制度について
現在の日本の公的年金制度は、2004年の財政検証に基づいて大改革が行われ、その後、幾つかの微修正が行われて来たものである。主要な骨子を挙げてみると、(1)国民年金保険料の水準を実質2017年度以降固定すること、(2)厚生年金保険料の料率を引上げ2017年度以降固定すること、(3)基礎年金の給付に必要な財源の半分を一般会計で負担すること、(4)少子高齢化の進展に対応したマクロ経済スライドによって、広く高齢者にも負担を求めること、などであった。一般会計による基礎年金の財源負担の恒久化は、自らを含む現在および将来の国民への負担拡大と考えて良い。一方で、厚生年金保険料率の引上げは、その後に実施された厚生年金加入対象の拡大も含めて、現在の被用者及び雇用主に負担の拡大を求めるものであった。また、マクロ経済スライドの実施による実質的な給付の目減りは、現在の受給者にも負担を少し求めるものであった。つまり、公的年金は広く国民全体に様々な負担の拡大を依頼することによって、制度の長期的な維持を図ったのである。
ところが、その際に打ち出された「100年安心」という説明が独り歩きして、“公的年金だけで老後の生活は100年安心である”といった誤った認識が広まり、その後のマクロ経済スライドの実施等に際しては、強く世論やメディアからの批判を受けることになった。誰しも多くの給付を受取れるのであれば、それに越したことはない。しかし、将来的に少子高齢化が進行するのであれば、高齢者の老後を支える現役世代の負担は、間違いなく相対的に拡大する。広く国民全般が痛みを分かち合うという主旨の公的年金改革であったが、「100年安心」というキャッチフレーズが誤解を招いてしまったことを否定できない。厚生年金等の積立金を運用し取り崩すことで、高齢化が進む中でも老齢年金の給付水準をある程度維持しようとする取組みであり、公的年金制度は100年経っても破綻しないという意味の“安心”だったはずである。決して個人が「100歳まで老後の生活は安心できる」などといった説明はされていない。誤った認識に乗っかり、年金受取額が実質的に目減りするといったメディアによる報道が、殊更に公的年金のイメージを悪くしているのではないか。
自助努力
これからの年金を受給するだろう世代は、公的年金への過大な依存は危険であり、自助努力が必要なようです。
それで、政府は新NISA(非課税で株取引が可能)を勧めたりし始めたってことですね。
松井証券の日本株取引~手数料0円から~自助自尊の精神で、やっていくしかないのかもしれません。
おわりに
政府や政治を批判したくもなります。でも、それでも何も変わりません。
これから自分にできること
選挙に必ず行って投票する。納得の行くお金の使い方をする。副業や投資をのために日々勉強をする。食べすぎず、飲みすぎず、間食を減らす。規則正しい生活。簡単なストレッチや体操。野菜・果物・ミネラル・ビタミンなどを摂取する。
思いつくことは、今これぐらいです。
重要なのは、健康とお金ですね。